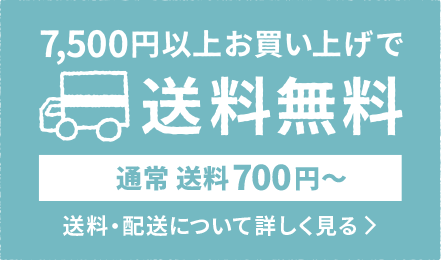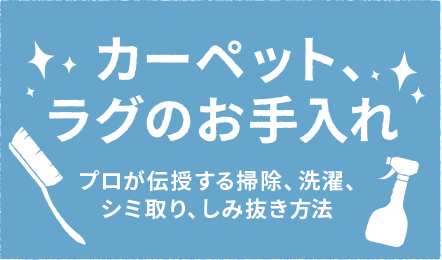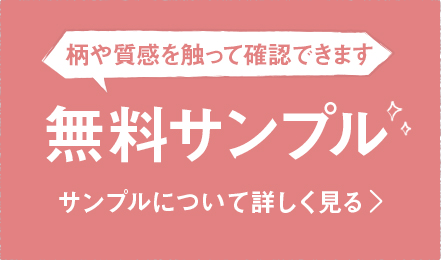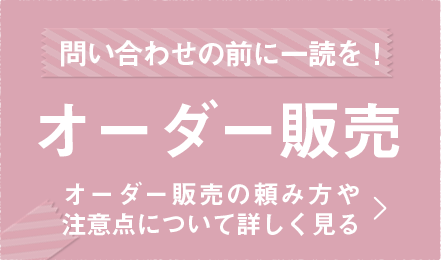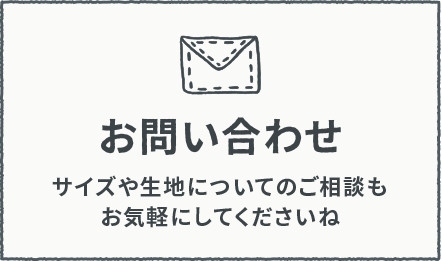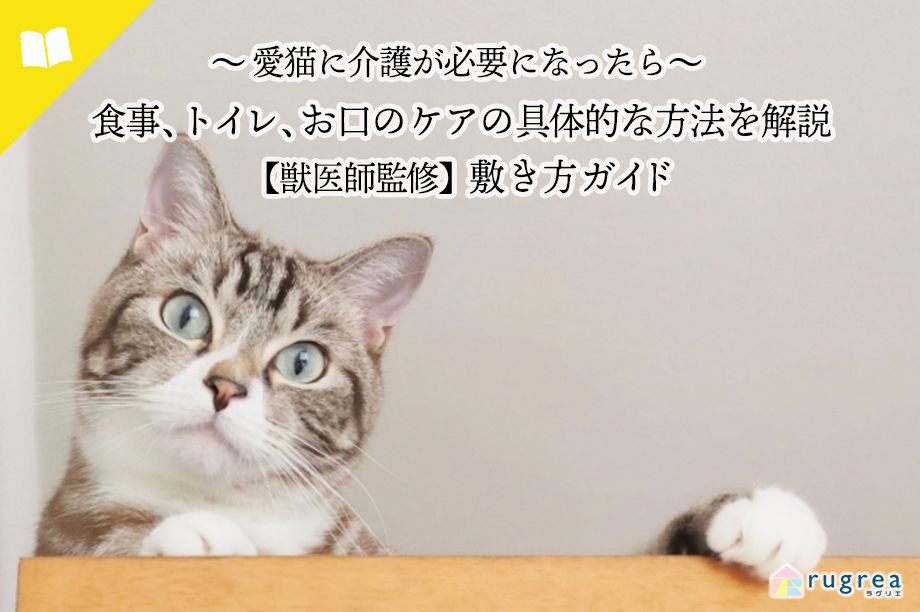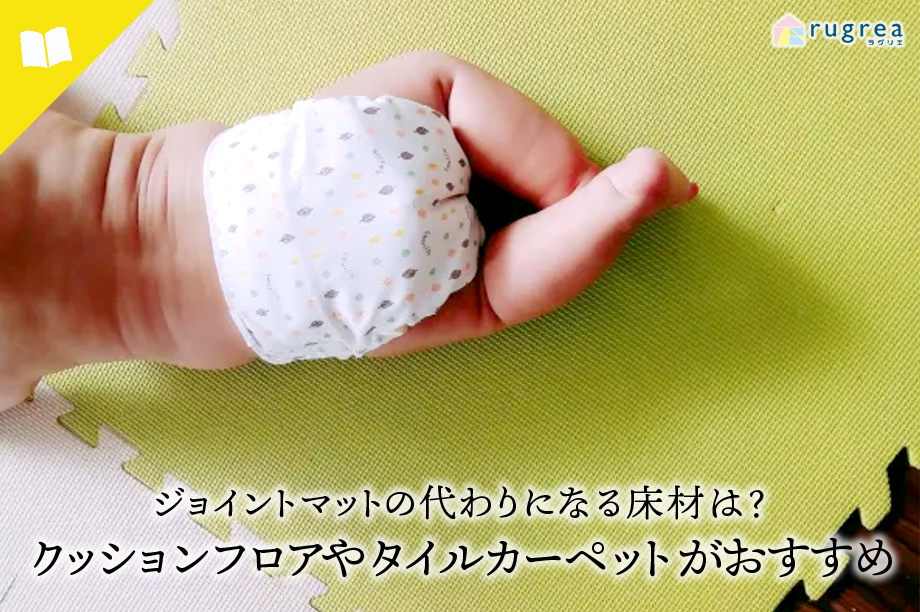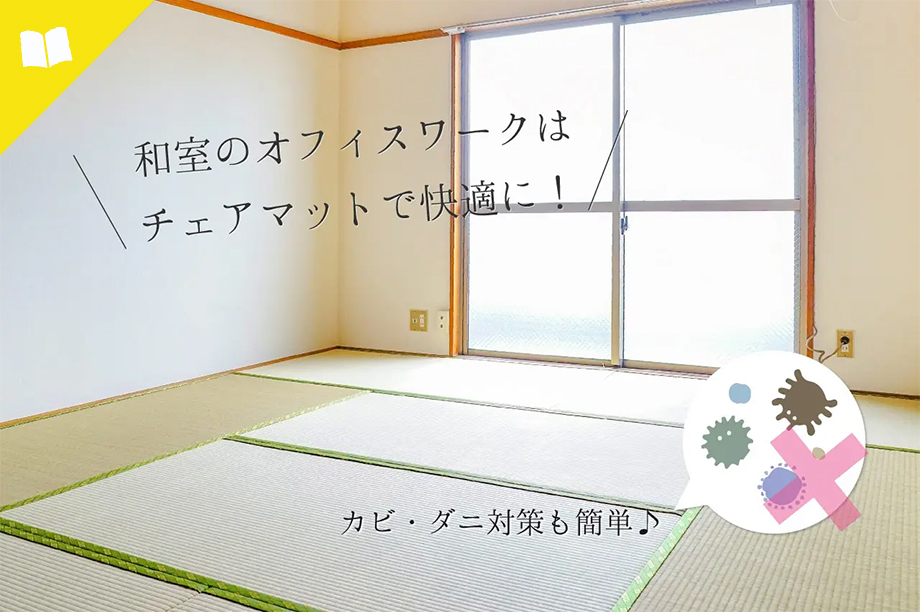玄関や店先、それに店内の壁などに飾ってあるドライフラワーの束が、何と呼ばれているかご存知ですか?
花束を逆さまにして吊るしているアレです。
答えは「スワッグ」
スワッグ(Swag)とは、「壁飾り」なので、よく壁に飾られているわけです。
冬になると針葉樹のスワッグをよくみかけますが、最近はドライフラワーで通年見かけるようになりました。
スワッグの作り方はとてもシンプル。束ねるだけです。しかし、美しく作るコツもあります。
そこで針葉樹が出回るこの時期。ご自身で作れる簡単なスワッグの作り方と、記念の写真撮影のポイントをご紹介させていただきます。
もくじ
スワッグとは
「スワッグ」とは、ドイツ語で「壁飾り」を指します。
ヨーロッパでは古くから教会の祭壇や家の壁などに飾られていたことから、リースと並んでクリスマスの伝統的な飾りのひとつになりました。
スワッグにも使うモミなどの針葉樹は、一年中緑色が絶えない常緑=「エバーグリーン」
つまり「永遠の命」を表すので、「魔除け」になると伝えられていることから、玄関に針葉樹のリースやスワッグを魔除けとしても飾ります。
生花や生木から作るスワッグは、生からドライになる過程を楽しむことができます。花や木の種類にもよりますが、2~3週間ほど吊るすことで水分がなくなり、ドライフラワーになります。
生花や針葉樹のみずみずしい美しさと香り、ドライフラワーになった花や木の美しさも楽しめることが、スワッグを手作りする楽しみであり特権です。
スワッグと似た形でガーランド(Garland)があります。
インテリアの壁掛けとして浸透してきたスワッグですが、作り方の違いで区別することもあります。一か所で束ねたものを「スワッグ」。
一方、花や葉や枝などを紐などで繋げたものを「ガーランド」と呼びます。
それでは、スワッグの作り方をご紹介します。
\写真背景にもぴったり/
準備
針葉樹だけでも美しいスワッグができますが、今回はボリュームがでるように複数の材料を用意しました。
【スワッグの材料】
・ヒムロスギ:2本
・ブルーバード:2本
・ヤシャブシ:1本
・ネズの実:2本
・ブルニア(シルバー):1本
【資材】
・輪ゴム:2本
(見やすさのため白い輪ゴム使用)
・麻紐:約 1m
・リボン:お好みの長さ(今回は1.5m)
【道具】
・枝切りハサミ
スワッグの作り方
束ねるだけですが、枝は一つとして同じものがありません。素敵なスワッグを作るためにやっていただきたいこと、気を付けていただきたいことなどを順番に説明します。
STEP.1 枝の選定
メインにする長く形の良い枝を選びます。
他の大きく枝分かれした枝は、根元からカットして分けておきます。
今回は、1本のヒムロスギが大きく枝分かれしていたので、切り分けました。
STEP.2 余分な葉や枝をカットする
持ち手になる部分の、余分な葉や枝をカットします。
STEP.3 長めの枝を束ねる
メインに選んだ長い枝を軸にして、その上に長めの枝を置いていきます。さらにヤシャブシを置き、残りの枝も上置きます。
もし枝の長さが同じくらいなら、少し上下にずらすことで、スマートな形になります。
形が決まったら輪ゴムで仮留めをします。
STEP.4 短い枝や木の実を束ねる
短めの枝の中から、なるべく長めの枝を下にしてから、残りの枝や木の実が付いた枝をおきます。
このときも同じ高さにばかり木の実が並ばないように枝を上下にずらりして、木の実がよく見えるように調整します。
結び目に近いところにポイント(今回はブルニア)が来るように実や枝を置いてから、輪ゴムで仮留めします。
STEP.5 まとめて縛る
長い枝の束を下にして、その上に短い枝の束を乗せて麻紐でしっかりと結びます。輪ゴムが隠れるほど麻紐をたくさんまいてください。
【結び方】
1.左手の親指で短い方の紐①を押さえ、右手で長い方の紐②をぐるぐると3~5回ほど巻きます。
2.①②を持ち、左右に紐を振り、紐を締めます。
3.最初に親指で押さえていた①を上に仮置きし、②を手元の方からぐるぐると3~5回ほど巻きます。
4.①②を持ち、左右に紐を振り、紐を締め、最後に固結びします。
※ 枝はドライになると瘦せてくる(細く)ので、枝がずれないように麻紐でしっかりと巻いてください。
STEP.6 リボンを結ぶ
麻紐の上にリボンを蝶々結びします。
今回は冬のイメージのリボンで装飾しますが、麻紐のままでも素敵です。夏にリボンを取り外し、麻紐を見せて飾るのもいいですね。
スワッグの飾り方
スワッグは壁に吊るすのが基本ですが、それ以外の飾り方を楽しむことができます。
スワッグを壁に吊るす
スワッグを壁に吊るして緑を空間に取り入れることで、お部屋が明るくなり、おしゃれな雰囲気に仕上がります。
壁にフックをつけたり、画鋲で留めたりしてスワッグを飾る他にも、ドアに飾ったり、ロープを渡してガーランドのように吊るすのもおすすめです。
壁に穴を開けられないのでマスキングテープなどを利用される場合、ドライになってからにしましょう。
生木の水分が残っているうちは水分の重さがあり、マスキングテープだけでは落ちてしまうかもしれません。また風通しの良いところに吊るしておいた方がきれいに早く乾きます。
スワッグを棚に置く
壁にスペースがない、極力壁を傷つけたくない場合は、棚や机に置くだけでもいいのではないでしょうか。
細身に作ったスワッグなら、棚や廊下のニッチスペースにさりげなく置くのもいいですし、テーブルのセンターに置いて、センターピースにしてもテーブルを華やかに演出してくれます。
スワッグの撮影方法
ドライになったスワッグも素敵ですが、せっかくなので、みずみずしい状態のスワッグを記念撮影して残しておきましょう。
大きめの被写体をテーブルや床などに置いてスマホで撮影する際のポイントを紹介します。
構図Ⅰ
高さのあるものは、斜め上から見た角度(45度程度)から撮影することが一般的です。
カフェなどでよく撮影する着席してテーブルの上を見る目線と同じです。高さや奥行きを感じる構図です。
対して真上から撮影することを「俯瞰」と呼びます。
大きな対象の場合、端が切れても構わないので俯瞰も一度試してください。今回のスワッグは比較的大きいので、以降は俯瞰で撮影しました。
構図Ⅱ
スワッグを俯瞰で見たら、さらに画面の中央ではなく、少しずらして(3分の1の位置)雰囲気を出しましょう。
この構図は「三分割構図」とも呼ばれ、縦横3分割した線の交点に、撮りたい被写体を合わせます。そうすることで写真に安定感が生まれ、収まりがよくなります。
縦でも横でも同じです。
因みに前の写真は、被写体が真ん中なので「日の丸構図」と呼ばれています。
普段からこの構図を意識するため、スマホのカメラにグリッド(グリッド線)を表示しておくことをおすすめします。
iPhoneの場合は、設定 > カメラ > グリッド [グリッド]の項目をONにします。
他の機種もカメラ設定の中にあります。
写真の構図を考えるとき、水平や垂直がわかりやすいのでガイドラインとしても便利なので是非、活用してください。
また、中心に表示された2つの十字線が重なったとき、スマホの傾きが水平(地面と並行)になったことを表します。俯瞰で撮影する際には、十字線も参考にしてください。
露出補正
撮影途中で周囲の明るさが急に変わってしまうことがあります。
カメラは、画面に映る被写体や場所が一定以上明るいと暗く、暗い場合は明るく撮影しようとする特性があり、自動である程度の調整がなされますが、手動で好みの明るさに調整することができます。
露出補正は、スマホカメラの画面を指でタップすると、明るさ補正のガイド(太陽マーク)が表示されます。
ガイドを上下にスライドすることで明るさを調整できます。
iPhoneとアンドロイドのどちらの機種も同じ操作で明るさの補正ができます。
タップする位置は、被写体でピントを合わせたいところをタップします。
実は、撮影時の画面タップは「ピント合わせ」にもなります。
背景をボカしたい場合、このタップ位置がとても重要になるので、露出補正のついでにピント合わせも行ってしまいましょう。
撮影背景(下地)
被写体を撮影する際に、後ろに映り込む風景が「背景」です。壁面や床、被写体が置かれている台なども背景です。
その中でも被写体の“下”にあるものを「下地」と呼びます。
下地はあくまでも被写体を引き立てる脇役のため、目立つ必要はありませんが、色や質感でずいぶんと印象が変わります。
撮影背景(下地)にクッションフロアが大活躍!
今回の撮影背景(下地)には、すべてラグリエのクッションフロアを使用しました。
長いスワッグを撮影するために台を用意するのは大変なので、クッションフロアを床に敷いてみました。
固定せずに置いただけ。撮影したいイメージによって、クッションフロアの柄を取り替えられたのでとても便利でした。
お気に入りのスワッグを作ったら、ぜひ、撮影背景(下地)にもこだわって撮影してから、飾ってくださいね。
\写真背景にもぴったり/
================
ライター:MIHARU
WEBデザイナー&WEBライター&撮影(Canon EOS R)
こちらの記事もおすすめです↓↓↓
MIHARU
最新記事 by MIHARU (全て見る)
- お部屋で気になる愛犬のおしっこ臭|においの原因と対策方法 - 2024年9月16日
- 愛犬の歩き方がいつもと違う?|犬に多い疾患と予防策とは - 2024年7月15日
- アジサイをお洒落に飾るアイデアと撮影|撮影背景(下地)を変える楽しみ - 2024年5月20日