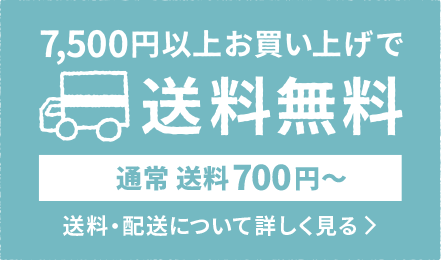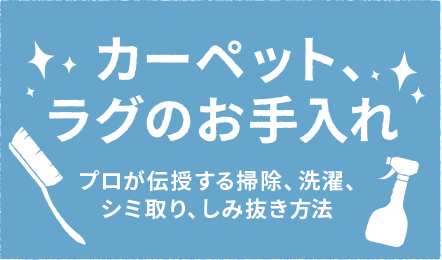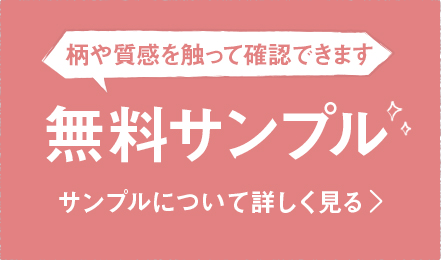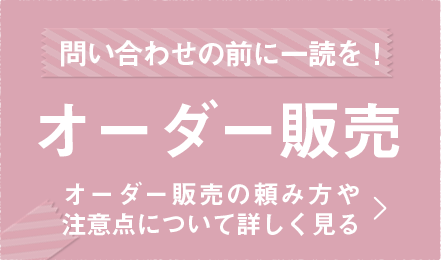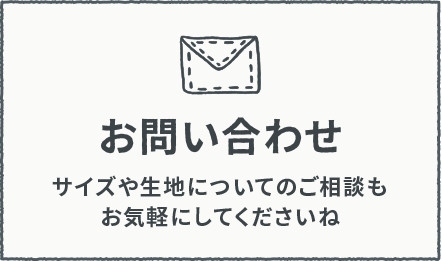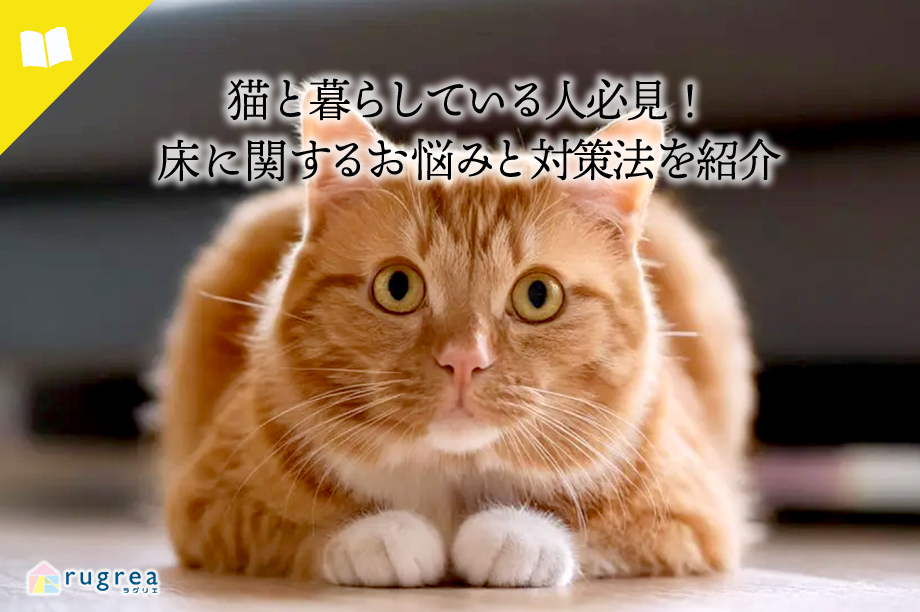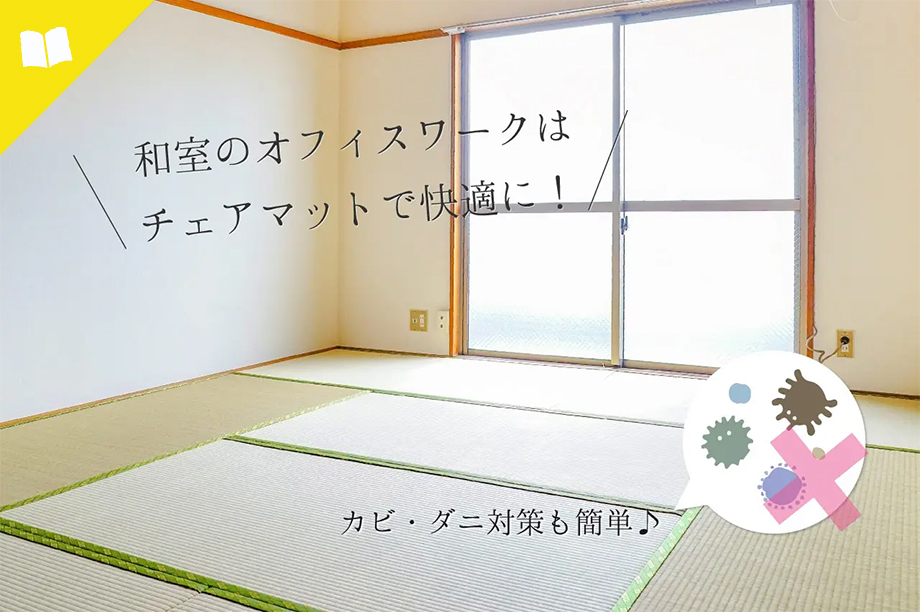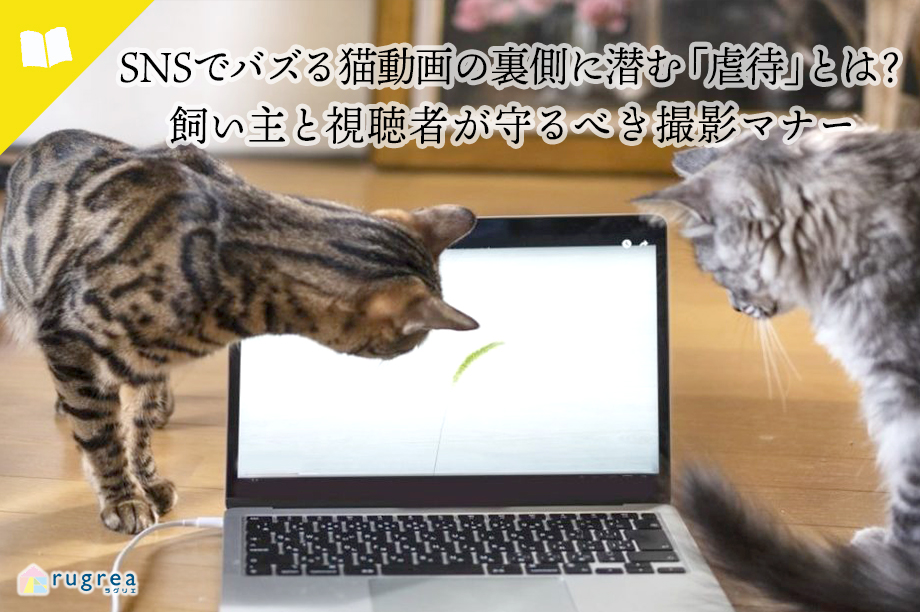水をはじく「撥水(はっ水)加工」がされたカーペットやマットがあるのはご存知ですか?
撥水加工がしてあるカーペットは、水をこぼしても染みこまず、玉になってコロコロと転がります。
では、カーペットについている撥水(はっ水)機能とはどんな機能なのでしょうか?
\デザインいろいろ!撥水機能付きで安心/
もくじ
カーペットやマットに使われる撥水加工の仕組みとは?
撥水加工と聞いて思い浮かべるのは、車のフロントガラスや雨の日の傘ではないでしょうか。
フロントガラスや傘についた雨粒がベタッと広がらず、コロコロと転がる──あの現象が、まさに撥水加工によるものです。
実はカーペットやマットにも、同じように水をはじく撥水加工が施された製品があります。

カーペットの上で水がコロコロと玉のように転がるなんて、少し意外かもしれません。水分が玉状になるこの現象、見た目の状態を「撥水」と呼びます。
撥水加工には、シリコン系やフッ素系の撥水剤が使われており、繊維の表面に薄い膜をつくることで水分を弾く性質を持たせています。
このコーティングがあることで、カーペットやマットに水が染みこみにくくなり、こぼした水分もサッと拭き取ることができます。
撥水加工はどうやってカーペットに施されている?
カーペットやマットに施される撥水加工は、布地や糸に撥水剤をコーティングすることで行われます。
一般的には、シリコン系樹脂やフッ素系樹脂といった撥水剤が用いられ、繊維の表面に薄い膜を形成することで、水を弾く性質を持たせています。
シリコン系はコストパフォーマンスに優れており、日常使いのアイテムによく採用されています。一方、フッ素系はより高い撥水性と耐久性を持ち、撥油性(油もはじく)にも優れているため、長期間の使用や油汚れが気になる場所に適しています。
このような撥水加工が施されていることで、液体が繊維内部に浸透しにくくなり、こぼした水や汚れもサッと拭き取るだけでお手入れが簡単になります。
撥水加工の効果はどのくらい?JIS規格の試験方法でチェック
撥水加工といっても、その効果にはレベルがあります。布の表面に水をどの程度弾くかを測るために、日本産業規格(JIS)が定めた試験方法が存在します。
それが「JIS L 1092(スプレー試験)」と呼ばれるもので、撥水性を数値で判断できる方法として、繊維業界や製品検査などで広く活用されています。
試験は、生地を45度の角度で固定し、上部から250mlの水を25〜30秒かけて噴霧。試験後、生地の濡れ具合を目視で確認し、以下のような5段階の等級に分類されます。
等級ごとの撥水性の目安
- 1級:表面全体が濡れており、水が浸透している
- 2級:表面の半分ほどが濡れ、小さな水滴が布を浸透している
- 3級:表面に小さな水滴状の濡れがある
- 4級:表面は濡れていないが、小さな水滴が付着している
- 5級:濡れも付着もまったく見られない、理想的な撥水状態
一般的な家庭用カーペットやマットでは、3級~5級程度の撥水性が備わっていることが多く、数字が大きいほど性能が高いことを意味します。
購入時や製品説明に「JIS L 1092 〇級相当」などと記載がある場合は、撥水性能の目安として参考にすると良いでしょう。
撥水と防水の違いとは?機能・仕組み・見分け方を解説
「撥水」と「防水」は、どちらも水を防ぐ機能ですが、仕組みや用途には明確な違いがあります。
ざっくりとした違いは以下の通りです。
- 撥水(はっすい):水を玉状にして弾く。生地の表面で水が転がる。
- 防水(ぼうすい):生地内部に水を通さず、完全に浸透を防ぐ。
撥水加工された生地の表面には「撥水基」と呼ばれる細かな突起状の構造があり、水分子よりも小さいこの構造によって、水を弾いて転がすことができます。
ただし撥水基は永久ではなく、摩擦や汚れ、経年劣化によって寝てしまうと、撥水効果が弱まることがあります。
一方、防水加工は生地の表面だけでなく内部まで水を通さないようコーティングされており、たとえ長時間水に触れても、裏側に水が染みることはありません。
代表的な例としては、
- 撥水:アウトドアウェア、タイルカーペットなど
- 防水:レインコート、長靴、ビニール製品など
見た目での見分け方は、水をかけたときに
- 撥水加工:水が玉状になってコロコロと転がる
- 防水加工:水が広がっても裏にしみ込まない
といった違いがあります。
また、撥水と防水は併用できないケースもあるため、用途に応じた素材選びが重要です。
撥水加工が弱まったときの対処法|熱で復活させる方法

撥水加工は時間の経過や摩擦、汚れの蓄積によって効果が薄れていきます。でもご安心ください。熱を加えることで、ある程度撥水性を復活させることが可能です。
手順①:まずは汚れをしっかり落とす
撥水性を回復させるには、まず表面の汚れを落とすことが重要です。
汚れが残ったまま熱を加えると、効果が十分に戻らないことがあります。
ぬるま湯や中性洗剤などでやさしく拭き、完全に乾かしてください。
手順②:ドライヤーやアイロンで熱を加える
生地が乾いたら、次は熱を使って撥水基を再活性化させていきます。
- ドライヤーの場合:温風を撥水性が弱くなった箇所に吹きつけ、生地表面がほんのり温かくなるまで当てます。
- アイロンの場合:生地のケアラベルを確認し、対応可能な場合のみ使用しましょう。
アイロンを使う際は、必ず当て布(タオルなど)を敷いた上から、110〜120℃程度の低温で軽く押し当てるようにして熱を加えます。
※目的はシワ伸ばしではなく「温めること」ですので、強く押し付けないようにしましょう。
処理が終わったら、実際に少量の水を垂らしてみて、再び水がコロコロ転がれば撥水性が復活している証拠です。
※クッションフロアは熱に弱いため、ドライヤーやアイロンでの加熱はお避けください。伸びや変形の原因となります。
すべての液体を弾けるわけではない?撥水加工の限界も知っておこう

撥水加工が施されたカーペットやマットは、水をはじくことで知られていますが、すべての液体を完全に弾けるわけではありません。
たとえば「油」は撥水加工でも弾きにくく、こぼした瞬間から生地に染み込んでしまうことがあります。
これは、水と油とで性質が異なるためです。撥水加工の多くは水性の液体に対して効果を発揮しますが、油のような油性の液体には対応しきれないのです。
とくに、キッチンマットやダイニング下のカーペットなどでは、炒め物の油やドレッシングなどが飛びやすいため、使用場所に応じた素材選びが重要になります。
撥水加工の特性を正しく理解し、水汚れと油汚れの違いを意識しておくと、お手入れや選び方の失敗を防げます。
撥水加工付きカーペットで、汚れに強く快適な暮らしを

水や汚れをはじいてくれる撥水加工付きのカーペットは、日々の掃除をぐっとラクにしてくれる頼れる味方です。
うっかり飲み物をこぼしてしまっても、染み込む前にサッと拭き取れるため、カーペットを丸ごと処分しなければならない…という事態を防げます。
見た目のデザイン性はもちろん大切ですが、機能性にもこだわることで、住まいの快適さは格段に向上します。
ラグリエでは、撥水加工を施したカーペットやクッションフロアを多数ラインナップ。北欧風、ナチュラル、モダンなどお好みに合わせて選べる豊富なデザインをご用意しています。
気になる方は、ぜひ一度チェックしてみてください。
\デザインも機能性も妥協しない/
==================
こちらの記事もおすすめです!
ゆかキチ
最新記事 by ゆかキチ (全て見る)
- ゆかキチの日常~キッチン扉にもクッションフロア編~ - 2020年6月18日
- 名古屋・栄「やば珈琲店」で名物・熱々鉄板ナポリタンを食す!【ゆかメシ】 - 2020年4月6日
- 人と部屋をおしゃれにつなぐフロアマット~2つをつなぐラグとマットの提案~ - 2019年9月6日